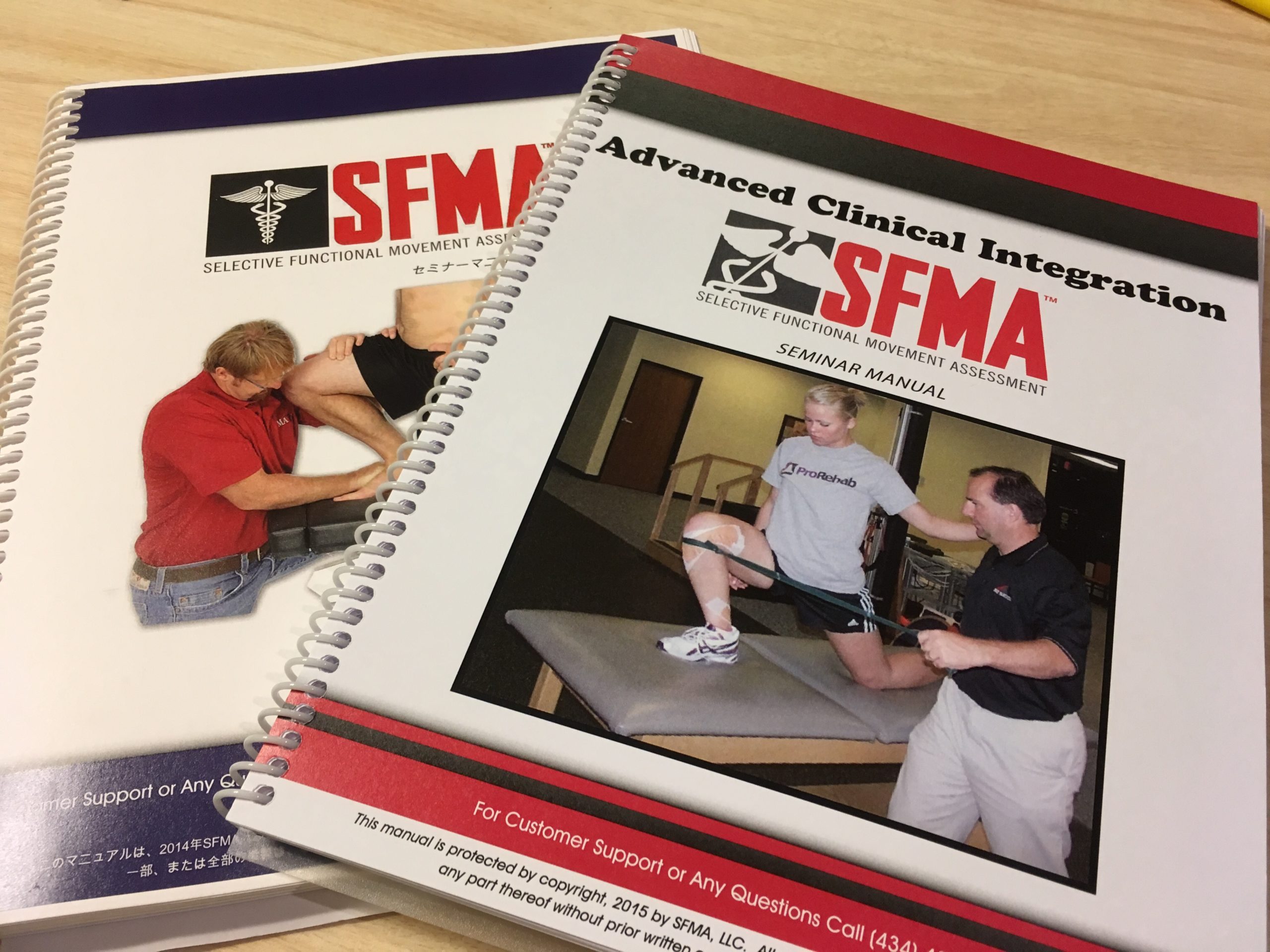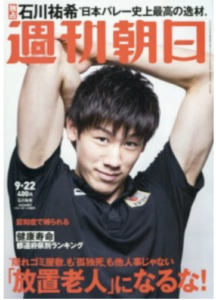SFMAの評価方法について
SFMAの評価方法について
いろいろセミナーを受ける中で様々な評価方法やスクリーニングがありますがl、今回はSFMA Lev.2 と呼吸のセミナーも受講しましたので、そちらの内容について簡易的に書いてみます。
まず、SFMAはSelective Functional Movement Assessmentの略で、google翻訳的には、選択的機能運動評価になります。Lve.1は評価方法をLvl.2は評価方法という流れで、Lev.1も知らない方もいるので、ざっと大まかに言うと(専門の方スミマセン)カラダの問題が
・関節なのか
・軟部組織なのか(最近でいう筋膜なんですかね)
・神経なのか(モーターコントロール)
をいくつかの動作を4つに分類(機能的で痛みなし、機能的で痛みあり、機能不全で痛みあり、機能不全で痛みなし)してテストを進めてていき、問題を把握することができるというものです。(例でいうと、肩が上がらないという人がいて、トレーナーが動かしたら上がるっていう場合は、原因はモーターコントロール。トレーナーでも上がらない場合は、関節か軟部組織。そのチャートがしっかりできてるのが、SFMA。)
今回はモーターコントロールの改善がメインでしたが、講師のカイルがやっているジョイントのテクニックやトリガーポイントや呼吸、PNFデモしてました。SFMAは評価までなので、基本的に自分たちのテクニックを使ってOKという感じです。
呼吸に関しては、PRIよりは、少し緩い感じがありましたが、基本的には呼吸しすぎで酸素が多すぎるということは似ているかなと思います。
修正エクササイズ
問題点の修正エクササイズの流れは、
・リセット(筋・腱・皮膚・関節などモビリティの修正)、
・リインフォース(テーピング・ホームエクササイズ・栄養・教育など)、
・リロード(運動学習)
をしていきます。今回はリロードに関してがメインとして、アプローチとしては、非荷重、四つん這い、膝立ち、立位の4ポジションに対して基本動作ができるか、できない場合リグレッションで促進系(アシステッド)かチャレンジ系をしていく流れで進めていきます。(さっくりでスミマセン。4×4エクササイズが、アップデートしてやや複雑になりました)
パワープレートはインプッットが回数が増えることでのメリットが高いので、適切なポジションでより効率的に行えるよう、エクササイズに問い入れる必要があるかとは思います。
カイルの話の中で印象的なのは、動作をして何度も『どんな感じ?』と聞いて実施者の主感を大事にしていたところ、新しいパターンができるようになったと感じてもらうことはすごく重要な要素かと感じました。また、関節か軟部組織かの判断のひとつとして走行の方向性についても話していたので、その辺は、自分で実感しながら確認していきたいです。
まとめ
上記でもまとめてますが、さらにまとめをしていくと、
・カラダの問題は大きく分けて3つ
・修正の介入も大きく3つ(今回の講習は運動学習メイン)
・モビリティテクニックは何でもOK、リロードは段階を踏みましょう
ということで、カラダの問題点を確認したい方は、Lightへお越しください